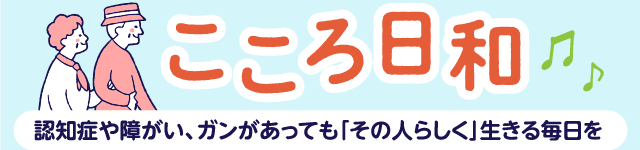ご家族の方から、
認知症であった旦那さんの介護を15年間してきて、先日他界された
とお話してくださいました。
「旦那さんを失った喪失感」
と
「自分自身の喪失感」
この2つの喪失感があり、気持ちを切り替えるのが難しいとのことでした。
これから、どうやって日々の生活を送っていったらよいのかと。
施設入所もしていたけれど、頭の片隅にはいつも旦那さんがいたとも話してくださいました。
この心が辛く苦しい時のための、「喪の作業」について、みなさんに知って頂きたいと思います。
「喪の作業」とは?
「喪の作業(grief work)」とは、大切な人を亡くした後に経験する、喪失の悲しみを乗り越えて、新しい生活に適応していく心理的なプロセスをいいます。
イギリスの精神分析学者フロイトが提唱して、その後、多くの心理学者によって発展してきました。
一般的に、喪の作業には次のような段階があります。
亡くなった人との新しい関係を築きながら前を向く
物理的には会えなくても、心の中で旦那さんとつながりながら、新しい人生を築いていくことです。たとえば、旦那さんとの思い出を大切にしつつ、自分のために新しい活動を始めることが一歩になります。この1歩がとても難しいと思います。半歩でも、1/10歩でも少しずつ、無理をせずに進みましょう。時には、立ち止まっても大丈夫です。その場に留まっているだけでも大丈夫です。答えを急がないことも、一つの勇気です。
喪失を現実のものとして受け容れる
愛する人が亡くなったことを、頭では理解していても、心が受け容れられないことがあります。
施設入所していたとはいえ、旦那さんは「生きがい」だったのかもしれません。
この「受け容れる」ということも大変な作業です。
一旦受け容れても、受け容れられなくなる時がきたりと、繰り返すことがあります。
私自身、精神障害と共に生きています。
20年以上経った今でも、受け入れがたいと感じる瞬間があります。
でも、それでいいのです。
慌てる必要はありません。
気心の知れる人と話をすることや、昔を懐かしむことができる歌を聴いてノスタルジア(過去を懐かしみ、切なさと温かさが入り混じる感情)を感じることが心を軽くすることがあります。
喪失による痛みを感じ、乗り越える
「旦那さんを失った喪失感」と「自分自身の喪失感」という二重の喪失があることが、悲しみを深くしているのではないかと思います。長年の介護によって、人生の中心が「旦那さんの存在」になっていたため、その役割を失ったという「喪失感」を感じることもあります。
心理学的に「乗り越える」過程が示されていますが、私は必ずしも乗り越えなくてもいいと思います。
悲しみや寂しさが、旦那さんを感じることでもあるからです。負の感情のようですが、旦那さんのことを思い出して涙することは、ポジティブな感情に繋がっていくと思います。
亡くなった人のいない環境に適応する
介護の日々が終わり、ぽっかりと空いた時間をどのように過ごすかが一つ課題になるかと思います。これは「亡くなった人を忘れる」ことではなく、新しい生活の中で「どのように旦那さんを思いながら生きていくのか」を模索する過程です。
喪の作業を進めるためにできること
- 感情を言葉にする
信頼できる人に気持ちを話すことが、喪の作業の助けになります。家族や友人、カウンセラーに「旦那さんがどれほど大切な存在だったか」「今の気持ち」を話すことで、悲しみを整理することができます。 - 「生きがい」を再発見する
これまでの生活は「旦那さんを支えること」が中心だったため、次の「生きがい」を見つけることが大切になります。無理にすぐ見つける必要はありませんが、趣味や地域活動に少しずつ関わることで、自分の人生を再構築できます。 - 亡くなった旦那さんとの「心のつながり」を持つ
旦那さんを想う時間を大切にしつつ、新しい日常を歩むことは矛盾ではありません。たとえば、写真を眺めながら感謝を伝えたり、旦那さんが好きだったことを自分の生活に取り入れることも、心の支えになります。 - 焦らず、少しずつ前に進む
「気持ちを切り替えなければ」と思うと、かえって心が苦しくなります。喪の作業には時間がかかるものです。「無理に変わろうとしなくてもいい」と思うことが、かえって回復を早めることにつながることもあります。
まとめ
ご家族が感じている「二重の喪失感」は、長年の介護と深い愛情の証でもあります。喪の作業は「忘れること」ではなく、「新しい形で故人を大切にしながら生きること」です。時間をかけながら、ご自身の人生を取り戻していけるよう、少しずつ進んでいけるとよいと思います。
もし一人で抱えきれないと感じたら、気軽にご相談ください。
https://t.co/M4NMNr0vEy