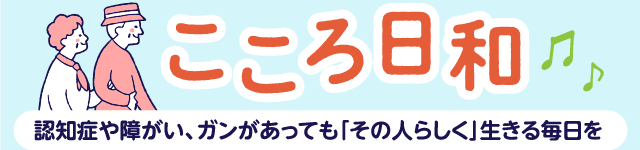統合失調症のこれまでの変遷と、認知症のこれからの変遷が似たように感じます。
統合失調症は、
・社会的スティグマの解消のために「精神分裂病」から「統合失調症」へ病名を変更
👉認知症も誤った認知症観を変えるため「痴呆症」から「認知症」に呼称変更
・「心の病か、脳の病か」という学術的な論争
👉「認知症は心の病か、脳の病か」というテーマは、学術的にも哲学的にも議論されてきた
・薬物療法への期待と高まり
👉認知症の進行を遅らせる新薬「レカネマブ」が開発される(2023年12月に保険適用)。
投与対象: 軽度認知障害(MCI)や軽度のアルツハイマー病患者が主な対象となります。投与には2週
間ごとの点滴が必要で、治療期間は18か月間とされています。
アルツハイマー病の進行を遅らせる効果が期待されている「ドナネマブ」(2024年11月に保険適用)
投与対象: アルツハイマー病による軽度認知障害や軽度の認知症が疑われる患者が対象です。投与開
始後12か月を目安に評価し、アミロイドβプラークの除去が確認された場合は投与を終了することが可
能とされています。
統合失調症は単一の疾患ではなく、統合失調スペクトラム症という見方を示しています(DSM-5:精神疾患を診断するための国際的なガイドライン)
このスペクトラムとは、「症状や特性が連続的に変化して、多様な幅を持つ状態」を意味します。
つまり、はっきりと区切られた病気ではなく、軽度から重度までグラデーションのようにつながっている概念です。
これは、認知症にも当てはまる概念だと思います。
認知症には、中核症状がありますが、個人個人症状や程度は異なります。また、これまでの生活歴や個性、環境によっても、BPSD含め、それぞれ違います。
このことは、認知症が、「心の病か、脳の病か」という点にも関係していると考えています。
現在では「脳の病であると同時に、心と社会の問題も含む総合的な疾患」という考えが主流になっています。医学・心理学・社会学が連携して認知症を多角的に理解しようとする「バイオ・サイコ・ソーシャルモデル(Bio-Psycho-Social Model)」が提唱されています。
バイオ・サイコ・ソーシャルモデルとは、「病気や健康を生物(Bio)・心理(Psycho)・社会(Social)の3つの側面から総合的に理解しようとする考え方」です。
たとえば認知症の場合──
- バイオ(生物):脳の萎縮、アミロイドβの蓄積など
- サイコ(心理):不安、うつ、性格、ストレス反応
- ソーシャル(社会):孤立、家族関係、福祉制度、文化的背景
これらが複雑に関係し合って、症状の出方や進行、生活への影響が決まるという考え方です。医療やケアにおいて、「脳だけでなく人としてまるごと理解する」アプローチです。
このように、認知症は「脳の病」であると同時に、「心の病」であり、「社会的な課題」でもあります。私たちは「個人としての認知症」に向き合う姿勢がより重要になってきています。
「認知症はこういうもの」と単一的に捉えないことが重要です。
あくまでも、今この社会に生きる一人の人として、心寄り添い合うかかわりが必要です。