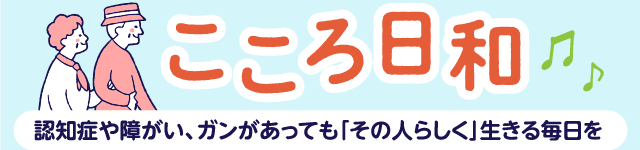人との関係が良いというのは、言い争いがないことでしょうか。
対立することがなければ、心は穏やかでしょうか。
どこかで気持ちを抑えたり、言いたいことを我慢したりすることにつながるのではないかと思います。
言い争いなどで、一時的に嫌な気持ちになったり、気持ちが昂ってしまうことはあるかもしれません。
しかし、その先で、相手の気持ちの理解に近づくことができ、「つながり」は強くなると思います。
そして、その方が心が穏やかになり、豊かになっていくと思うのです。
たとえば、会社で会議があったとします。そこで、みんな賛成意見で意見が飛び交うこともなく、物事が決まったとします。その答えは、本質を得たものでしょうか。
反対意見があってこそ、多角的に深く物事を見ることができて、本質に迫ることができます。
なんのぶつかり合いもない社会、社会性の中では、人間としての営みの質を希薄化させるのではないかと危惧しています。
一見平和な関係性を良しとする社会は、逆に生きづらさを生むと思うのです。
多様性も、様々な価値観などをもつ人を尊重することだと思いますが、それぞれが持つ価値観がどんなものなのかについて知る必要はあると思います。否定し合う必要があるという訳ではありません。
たとえば、
「わたしは、こういう価値観を持っている」
そのことについて、
「わたしはこう思うけど、そのことについてはどう思うの?」
といったような、「対話」があったら、多様性も深まると思います。
現代において「対話」が欠けていると思います。
人との関係性を深めるものは、「対話」だと思います。
しかも、様々な意見が飛び交う対話。
時にぶつかり合い、時に認め合い、そうして本質に迫っていく。
失われつつある本質的な「人と人との営み」が、育まれていくと思います。
そして、この「対話」によって、「社会的な豊かさ」と「心の安寧をもたらす」と私は思います。