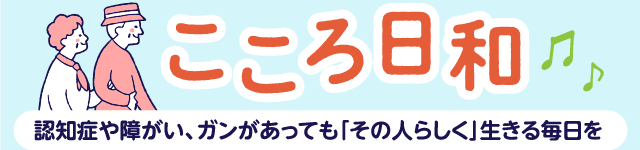お盆の時期になると、メディアの、戦争に関する報道を多く目にします。
戦争があったということは、語り継がれなければならないことかもしれません。
しかし、その報道を見ることによって、苦しんでいる方がいることを知っておいて欲しいと、
わたしは考えています。
お盆の時期になると体調を崩したり、精神的に不安定になる方がいらっしゃいます。
それは、もしかしたら、「戦後PTSD」が原因かもしれません。
「戦後PTSD」とは、
戦争体験の記憶や感情が、高齢になってからふたたび心に浮かび上がってくることです。
当時は、PTSD(心的外傷後ストレス障害。簡単に言うとトラウマのことです。)という言葉も
認知されていませんでした。
そのため、その心の傷に対するケアがなされないまま、現在に至っている方が多いのです。
PTSDというのは、海馬(脳で記憶を司る(つかさどる)ところ)と深い関係性があります。
なので、その海馬との関連性の高い、アルツハイマー型認知症の方は影響を受けやすいです。
そして、アルツハイマー型認知症の発症リスクとしても、研究で明らかにされています。
(アメリカの退役軍人18万人を対象にしたYaffeらの研究(2010)によると、PTSDを持つ人は、認知症を発症するリスクが約2倍高いことが示されています。)
介護施設でも、回想法(昔を懐かしんで心理的安定を図るもの)として戦争を取り上げることが
多くあるように感じます。
戦争体験を思い出すことによって、
・体験の記憶がより生々しく蘇る
・※「認知症」に影響して、混乱と重なり、「現在」と「過去」が混ざって、
戦時中に戻ったような行動(例:避難しようとする)がみられる
・トラウマが癒されていないため、感情の混乱、怒り、不安が強まる
※「認知症」とは症状のことです。
このような心理的負担が生じます。
なので、
・「戦争を語りたい気持ち」と「語ると辛くなる気持ち」の両面を尊重すること
・回想法を用いる場合も、安全で安心できる環境で行って、過去の体験を強要しないこと
・例えば、「戦後の暮らし」や「復興の努力」など、比較的肯定的な記憶に焦点を当てること
また、
「語らない」ことを自分を保つ手段としている方もいらっしゃいます。
なので、
無理に話を引き出さず、沈黙に寄り添う姿勢が、安心感を高めます。
もし、「フラッシュバック的行動」がみられたら、
否定せずに、
「大丈夫ですよ。もう安全な場所にいます」
という
「今ここ」の安全を知らせる声かけなどをして、
「安心感」を持っていただけるように努めることが大切です。
私たちが、持つべき視点として、
戦争を体験された方は、
・「自分が生き残ったという罪悪感」や
「何も語れなかった痛み」などの、
心の苦しみを抱えてらっしゃる場合があるということ。
・認知症の影響で、
うまく言葉にできなくても、
その感情は無意識の中で強く残っていることがあるということ。
こういった事実があるということを、認識しておくことが大切です。
だからこそ、
日々の「敬意」と「寄り添う気持ち」を持った関わりが、
心理的な支えになります。
この記事を、戦争体験をされた方が読んでいらっしゃるかもしれません。
苦しんでいらっしゃるその気持ちに、
今私がそばで寄り添うことも、
ただそばで沈黙をともにすることもできません。
その苦しみを、私は理解することもできません。
でも、
わたしは、理解することができないとわかっていても、
「理解をすることを諦めない」姿勢でいます。
ご家族様、介護従事者の方、様々な支援者の方、そしてメディア関係の方。
この「戦後PTSD」に苦しんでいる方がいるということを、
心に留めておいて欲しい。
その一心で、この文章を書いています。
そして、この記事を読んでいただいた方の周りで、
「戦後PTSD」を知らない方がいたら、
その方にそっと教えて欲しいです。
静かに、
でもしっかりとみなさんの心の知識として持っていただけたらと
切実に願っています。