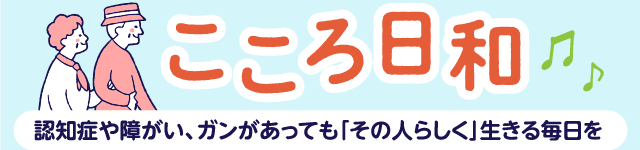私は、大学時代(20年以上前)精神保健福祉を専攻していました。
その時、「幻覚妄想の話は聞いてはいけない」「肯定も否定もせず受け流すように」と教えられてきました。
しかし今、そういった考え方が変わろうとしています。
「病的でもそうでなくても、どんな発言も重要だ」という立場をとる、「※オープンダイアローグ」が注目されています。オープンダイアローグでは、発言にぐっと踏み込みます。「その話をもっと聞かせてください」とこちらから、相手の思考の歯車の中に飛び込ませてもらうのです。
※オープンダイアローグ:対話を通じて問題を共有し、即時の解決よりも関係性や理解を深めることを重視するアプローチ。
大切なのは、「話を聞いてくれる人」という「伝わった感」を感じてもらうことです。
精神病理学者の木村敏さんは
「治療の目標は、患者が私たちの生活者の仲間になること」
と、おっしゃっています。
普段わたしたちは、目的をもって会話をするというより、興味や関心を持って会話をしていると思います。
それが、治療やケアになると、「患者」、もしくは「利用者」としての興味しか持たれずにいます。
「その人」としての興味をもった会話が希薄になります。
臨床哲学の鷲田清一さんは、
「私たち固有のかけがえのなさは、他者との関係において、誰かから名前を呼ばれる、という瞬間に成立する」とおっしゃっています。
たとえ、認知症であっても、メンタル疾患をもっていても、「一人の人」として、名前を呼び合う関係が必要です。それが、欠けている、もしくは失われている状態である方が、多くいらっしゃるように感じます。
鷲田清一さんは
「語り合えば語り合うほど、他人と自分との違いがより微細にわかるようになること、それが対話だ」
と、おっしゃっています。
だからこそ、オープンダイアローグが必要なのだと思います。
今、「多様性」という言葉、概念が広まっています。色々な人がいるから、様々なハプニングが生まれ、そこから進化していくことができる。
対話というのは、人と人との関係に新たな糸口を見つけるための一つの手段です。
バフチンという人の「※ポリフォニー」の概念は、そのようなことを含んでいるのだと思います。
※ポリフォニー:多様な声の共存
人は、人間関係のなかで揉まれることによって、自分のとげとげしかったものが、取り除かれて丸くなっていくのだと思います。
しかし、その人間関係が、現代では、リアルで会うことが減り、地域とのつながりも減り、希薄になっているように感じます。
とげとげしいまま人生を歩んでいくことで、人間関係に難しさを感じ、「生きづらさ」を生んでいるのではないでしょうか。
その「生きづらさ」を解消するためにも、オープンダイアローグが必要だと思います。
オープンダイアローグの原則に
「不確かさに耐える」
というものがあります。
何かしらの課題があり、目の前に壁が存在している。でもその壁のまえで、ウロウロとしていればいいのです。ただ、「どうしたらいいか」と試行錯誤しながら、その場所に留まり続けるのです。
そのためには、壁の向こうの希望に気付くことです。
私たちは、その希望をどう作るか。それが課題ではないかと思います。
参考文献
https://amzn.asia/d/46wXXa4
ピアカウンセリングのご案内📣
私自身、双極性障害をもって生活しています。
同じ悩みを語り合うことで、心が軽くなります😊
ご興味ありましたら、こちらからお申込みください👇
https://t.co/M4NMNr0vEy