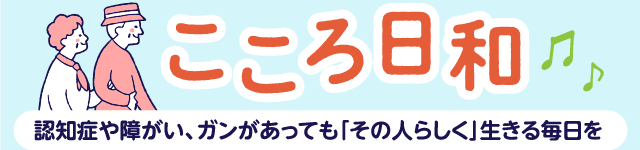「パーソンセンタードケア」という言葉を聞くと、
多くの方は“認知症ケアの専門的な考え方”を思い浮かべるかもしれません。
しかし、その原点はもっと深く、
そして、もっと普遍的な場所にあります。
🕊 パーソンセンタードケアの原点は「すべての人」
パーソンセンタードケアは、
アメリカの心理学者カール・ロジャーズの提唱した「パーソンセンタード・アプローチ」に由来します。
彼が伝えたのは
「どんな状況にある人も、尊厳と成長の可能性をもつ存在である」という、人間観でした。
つまり、これは特定の病気や障がいをもつ人だけの考え方ではなく、
すべての人に共通する“人間としての在り方”そのものなのです。
イギリスの心理学者トム・キットウッドは、
このロジャーズの哲学を認知症ケアに応用し、
「認知症の人を“患者”ではなく“一人の人(Person)”として尊重する」ことを訴えました。
けれども、私はこう考えています。
「パーソンセンタードケアとは、“認知症をもつ方のためだけのケア”ではなく、“人と人との営み”そのものの在り方である」と。
🌿 「創痍」に寄り添うということ
人は誰しも、心の奥に“創痍(そうい)”を抱えています。
それは、癒えない痛みや、誰にも語れない寂しさの記憶です。
しかし、それは弱さではなく、
“まだ世界とつながりたい”という証でもあります。
認知症ケアの現場で感じるのは、
ご本人の、いわゆる「不可解な言動」の裏には、
いつも“心の創痍”があるということです。
怒りや混乱は、崩壊ではありません。
それは、創痍としての心の痛み(ミクロ)が行動(マクロ)として現れているのです。
そしてこのサインを受け取るために必要なのが「対話」です。
💬 「対話」は、相手の世界を見に行くこと
「対話」とは、相手を変えるための手段ではありません。
相手の価値観を否定することなく、その安心感の中で語り合うコミュニケーションです。
認知症ケアにおいて、この「対話」が「共感」として在ることが必要です。
怒りに寄り添うときは、優しさではなく「怒りの感情」で。
悲しみに寄り添うときは、慰めではなく「悲しみの感情」で。
それが、嘘のない共感。
誠実であり、その場しのぎでもない。
人としての在り方が問われます。
「誠意をもって感情に寄り添う」という在り方。
これは、心のグルーオン(見えない糊)のように、
人と人とを再びつなぎ合わせる力になります。
創痍は、ただ癒すものではなく、
「対話」という「共感」を通して“昇華される”ものなのです。
🌙 「すべての人」が中心にある社会へ
パーソンセンタードケアの本質は、
「認知症の方を中心に」ではなく、
「すべての人を中心に」という思想にあります。
認知症の方も、支援者も、ご家族も。
誰もが、それぞれの痛みと創痍を抱えて生きています。
だからこそ、支援とは「誰かを助けること」ではなく、
「互いの創痍に寄り添い合うこと」なのです。
ケアは、一方的に与えるものではなく、
“being with(共に在ること)”という関係性の中にあります。
それが、ケアシェアラーという在り方なのです。
🌸 創痍と対話の先にあるもの
私たちは皆、それぞれの人生の中で、
失うことと、残ることの両方を経験します。
認知症とは、“失う病”ではなく、
“残るものと生きる病”です。
残るもの――それは感情記憶。
喜びや安心、愛情や希望は、最後まで心に宿り続けます。
創痍を抱える人に寄り添うことは、
その“残るもの”を見つめる旅でもあります。
そして、その旅の道標となるのが、「対話」です。
🕯 終わりに ― 「対話」の中で再びつながる
創痍を癒すのではなく、
その痛みの中で“自分と再び出会う”ことです。
それが、セルフバリデーションであり、
パーソンセンタードケアの本当の意味でもあります。
私たちはみんな、誰かの痛みとつながりながら生きています。
そのつながりをもう一度信じるとき、
認知症の方も、ご家族も、支援者も、
“自分らしく生きる”という同じ地平に立てるのです。
創痍と対話。
その間には、「感情に寄り添う」という、人間の尊厳と希望を守り、再生するための「共感」が確かにあります。実態として見えなくても、グルーオンのように実在しています。
目に見えるものよりも、目に見えないもを感じることが、
創痍を癒していくのです。